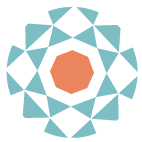バイクが縦横無尽に走るジャカルタの賑わしい道でタクシーに揺られながら、いまこのチームのみなさんと一緒に行動し、どっぷりと時間を過ごしている自分の状況が、ふと強烈に面白く感じられてきた。「あれ…?なぜ私はいまここにいるんだっけ?」という、根源的かつすこし浮遊感をともなう気分がこみあげる。フィールドワークや海外渡航を何度も経験してきた私にとってさえ、今回の旅は多くのことが新鮮で刺激的だった。もちろんここに至るまでには、幸運な出会いや知的好奇心に根ざした選択などの経緯があり、この調査の旅もそこから生まれた形のひとつにすぎない。それにしてもやはり、私に良い意味での強い戸惑いをもたらすほどに、この旅は新鮮で刺激的だったのだと思う。
これまで行ってきた人類学の調査=フィールドワークでは、未知の場所に単独で赴き、そこに暮らす人と出会い、そこで生じるさまざまな出来事を観ては、その世界の中で一緒に長い時間を過ごしながら、ものを考えてきた。そして彼らの認識に少しでも寄り添うことを試みつつ、私と彼らの関わりのなかで立ち現れる何かをつかみ取ろうとする。簡単にいえばそんな行為の積みかさねだ。ともかくそれは、フィールドで出会う人びととの関わりを除いては、調べることも知ることも考えることも基本的に個人作業だった。このように海外のある土地で、チームで一緒になって調査するというのは初めての経験である。それだけではない。どうやらこのチームのみなさんは、人類学者の私が調査の現場で何をどうやって観るのか、いったい何を考え、何を選び、どのように対象を「わかって」いくのかについて、とても興味があるのだという。つまり今回は、「ジャカルタの暮らしを観る人類学者の私を、チームのみなさんが観る」という、奇妙な入れ子構造 のなかで調査が進められた。それがこの2日目のことだ。
今回のキイワードを「ジャカルタ(インドネシア)」「食」「健康」とすると、実は私はいずれの専門家でもない。テーマに応じた専門家が同行しチームに適切なアドバイスをするという構図は一般的にもイメージしやすいものだけれど、それに当てはまらない人類学者を同行させているこのチームのみなさんも、私からみれば何だか変わった人たちである(それはもちろん良い意味で、野心的だと思う)。こういった状況のなかで自分が果たせる役割はといえば、それは「はじめての調査対象との出会い」のなかで、
対象への理解が発生していくプロセスを、方法論とともに詳細に見つめなおすこと だと思った。もはや私自身も無意識のように進めてしまいがちな調査というものを、チームのみなさんと一緒に経験しなおし、お互いに気づきを共有しながら、
これまであまり言語化されてこなかった行為を言語化してみる。これは私自身にとってもたいへん貴重な機会だった。
事前に準備を進める段階で「比嘉さんは現地でどこを観たいですか?」と尋ねられたとき、思わず考えこんでしまった。いつも自分はフィールドでどこに足を運び、何を観ていたのだろうか?一般的に調査対象というのは調査のテーマや目的に応じて定まっていくものだし、特にマーケティングなどビジネスのリサーチであればまずクライアントの要望が前提としてあるため、それに沿って設計されるはずだ。しかしアカデミックな研究活動においては、誰かがテーマを決めてくれるわけでも、事前に用意された項目があるわけでもない。それは自分自身の興味関心を出発点として、既存の研究や情報を参照するなかでぼんやりと定まってくるものだ。特にフィールドワークのような現場で何を観るかといったレベルの細かい選択に関していえば、
これまでの様々な調査の経験を拠り所にした「嗅覚」みたいなもの も、おそらく総動員していると思う。
そしてさきほどの問いに対して出てきた私の答えはとても単純なものだった。
「人が集まるところを観たいです、たとえば市場とか。個人個人を観るのではなくて、そこに集う人たちのあいだで、会話ややりとりが生まれているような生活の場面を観たいです」
結局その日の私たちは、まず朝から伝統薬(jamuジャムウ)を提供するカフェに行き、そこから街を散策して市場(pasarパサール)へと向かった。伝統薬のカフェは出発直前にその情報を見かけて急遽行ってみることにしたのだが、それはジャカルタの人びとの健康観にアプローチするという調査の目的にも、そしてそこに人びとが集う様子を観たいという私の希望にも、適っている気がしたからだ。訪れたカフェは落ち着いた雰囲気で、カウンターの奥に並んでいるものが薬の入った瓶やケースであり、そこにいる客が飲んでいる飲み物が明らかにお茶やコーヒーではない茶色い液体であることを除けば、まるで普通のカフェのような趣だった。私たちも店内に入り、奥のテーブルに腰掛けてメニューをもらった。番号順にずらっと並んだ飲み物の名前と解説は当然インドネシア語で書かれており、私にはその意味がさっぱり理解できない。店員の女の子に
「この店のおすすめは何ですか?」と尋ねてみると、少し戸惑った表情の彼女は、いったん奥に戻って店主に聞きにいってくれた。そして返ってきたのは「おすすめというのはありません」という答えだった。
よくよく説明を聞いてみれば、「この店のメニューとは、訪れた客がそれぞれの症状に合わせて選ぶべきものであって、一概に何が良いと言えるようなものではない」という話だった。そのとき身体のどの部位に不調があるのか、それはどのような症状なのか、といった個別の状態を伝えてはじめて、それに応じた最適なメニューを勧めてもらえる。
ジャムゥとはあくまでも「薬」なのだから、症状と薬に対応関係があることなど考えてみれば当たり前の話なのだが、一見するとカジュアルなカフェの雰囲気につられて、思わず私も「おすすめ」を尋ねてしまったのだった。そう、なんとなく端から見て想像しているだけではなく、こうして直接的に経験し、
相手から自分の認識(思い込み)を書き換えてもらうことの積みかさねによって、私たちはだんだんと世界を「わかって」いく のだと思う。
ある程度の時間をかけてグラスを空にしてから店を出ると、私たちは近くの市場へと向かって歩きはじめた。その道中にも様々な店が建ち並び、賑やかな通りがつづく。炎天下のなか歩いている自分たちのような人間は少数派だが、車やバイクの往来は途絶えることがない。コーヒー豆を販売する店を通りかかったので店先の人に焙煎場所を尋ねてみたり、食堂のなかで従業員と思われる女の子たちがお喋りしながら大量のニンニクの皮をむいている、その手作業の様子にふと目を留めたり、飲み物を売る屋台にぶら下がったカラフルな粉末飲料の小袋をしげしげと眺めたり、何か気になることがあればどこでも足を止め、様子を眺め、そこから人びとの暮らしを読みとろうとした。
もちろん言葉(インドネシア語)がわからないことは大きな壁だ。店の看板やパッケージのラベルひとつとってみても、多少推測するにせよ結局は手元の翻訳アプリに頼らなければ読めないし、ふと目の合った人に対して微笑みこそすれ、気軽に話しかけることもままならない。
人類学の調査であれば調査対象の人びとの言語は徹底的に習得していくものだけれど、ビジネスのリサーチでは時間的な制約もありなかなかそうはいかないだろう。通訳の方に入っていただくことでこの問題の一部は解決するが、
言語とは単なる情報収集のための道具ではなく、コミュニケーションを通じて相手と関係性を構築するための道具
でもある。もっとインドネシア語が話せれば良かったのに、と正直何度も思った。けれどもその一方で、言語ばかりに依らなくても、観察をしたり、記録をしたり、身ぶりや手ぶりで乗り越えられる部分も確実にあって、その領域を意識化していくことにもまた別の意味があるだろう。そして人類学者であっても、言語を習熟する初期段階ではこうした状況を必ず経験しており、その意味では、じつは誰もが通る道なのだ。
しばらく町歩きを続け、私たちが目指していた市場(pasarパサール)までもうすぐというとき、ひとつの屋台に目がとまった。屋台の上のカゴには天ぷらのような物が何種類も並んでいて、なんだかおいしそうだ。店主はその前で黙々と、天ぷらを揚げつづけている。商品である食べ物自体への関心もあるが、やはりそれを作る人間とその作業の様子に強く興味をそそられる。その手元をじっと眺めていると、彼は慣れた手つきで油の中から溜まった天かすをすくいあげては脇に置き、こんがりとキツネ色になったキャッサバらしきものの揚がり具合を確認すると、手際よく並べていく。他にも平たいイモ天のようなものや、練り物のような揚げ物など、その外見からは中身が推測できないものもたくさん並んでいる。
得体の知れないその揚げ物は、とりあえずいくつか買って食べてみることにした。調査のときに限らず旅がまさにそうであるように、実際に現地の人から直接何かを買ったり食べたりする経験は、ただそれについて見聞きしているだけのときよりも、はるかに多くの情報を私たちにもたらす。
お金やモノのやりとりという物理的なインタラクションが生じるのはもちろん、それに付随する何気ない会話やその場の雰囲気、感覚など、言語化しきれない無数の情報が一気に飛びこんでくる。
このときに買った揚げ物はそのすぐ後に皆で分けあって食べたが、私にとって興味ぶかかったのは実はその包装だった。おそらく何かの書類であろうコピー用紙を再利用し、糊で貼って作った「紙袋」は形も歪んでおり手作り感に溢れていた。てっきり既製の袋やパックに入れてくれるかあるいは簡単に紙ナプキンなどにくるんで渡されるかと思っていたので、それは少し意外なかたちだったのだ。とても些末なことだけれど、こうした
自分の想像を超えるような細部に触れるときこそ、人びとの暮らしや商売の作法、価値観の片鱗を垣間見ることができるように思う。
ようやく目的の市場に到着した私たちは、建物の一角にある小さな売店で休憩した後に、階下に広がる市場を散策した。地下の市場は少し薄暗く、小さな店が連なる細い通路をたどるように進むと、やがて奥の様子が見えてくる。そこには野菜などの生鮮品からお菓子などの食料品、調味料、そして洗剤などの日用品まで、多様な商品が所狭しと並んでいる。商品の種類は異なっていても、その販売のスタイル、つまり
モノが小分けにされ軒先に整然と吊されている様式はあちこちの店で共通
していて、それはこの旅全体を通して特に印象的な光景のひとつだった。小分けにされていたのは既製品だけではなく、唐辛子などの調味料を売る店でも、菓子を売る店でも、山積みにされた品物は一見量り売りのようであるが、店の人がそれを丁寧に小さな袋に詰めて、それらを器用に軒先に吊しておく。そうやって吊されたモノたちは天井にぎゅうぎゅうとひしめきあい、雑然としているようでどこか美しくもあり、その光景が今もふっと脳裏に浮かぶとき、ジャカルタの生活をごく一部だけれど自分の体内に宿したような、そういう気分になるのだ。
そして私たちは、ホテルへの帰路についた。