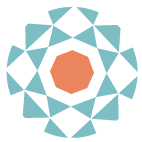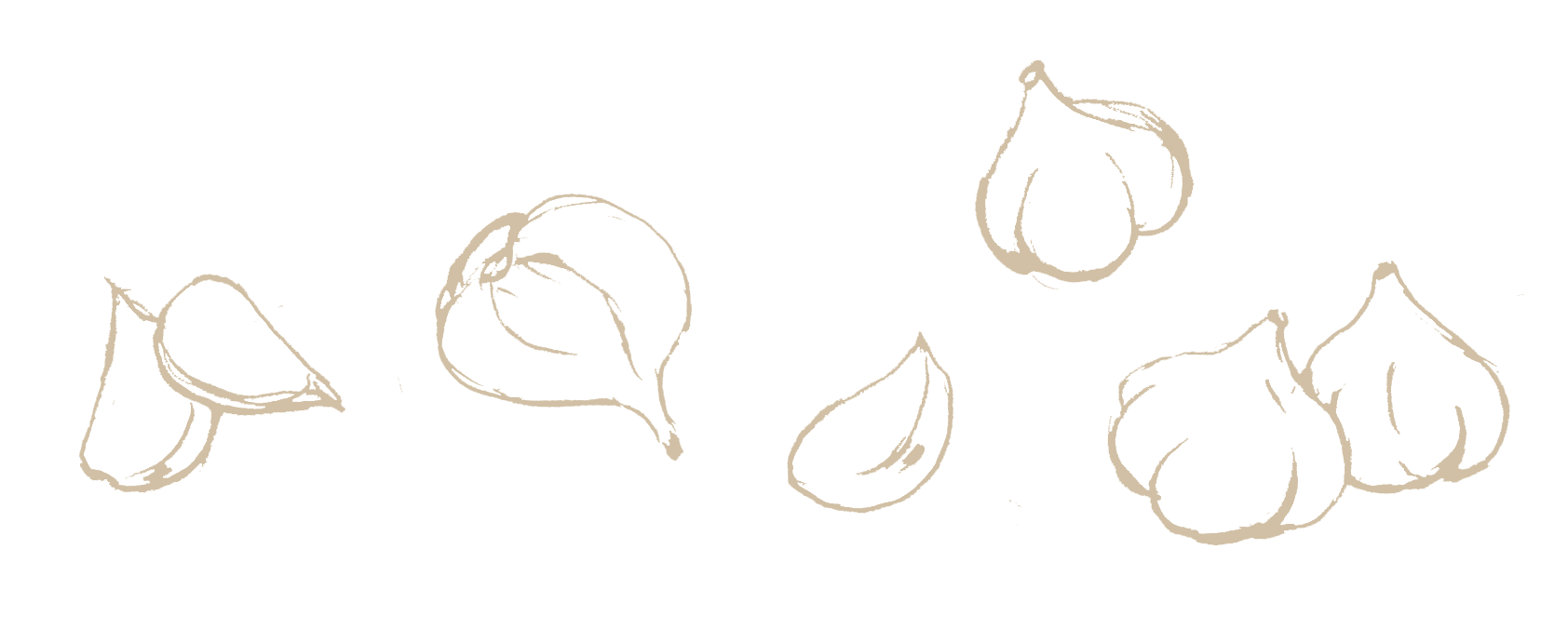Report by UCI Lab. #1
フィールドワーク編
コミュニケーション回路をひらくプロセスはショートカットできない
 UCI Lab. 所長/ディレクター
UCI Lab. 所長/ディレクター
渡辺 隆史
-----------------------------------------------------
「聡明」で「軽やか」。もし比嘉さんを誰かにひと言で紹介するならそんな言葉になるでしょうか。しかし、ジャカルタでのフィールドワークの最中にわたしが目撃していたのは、もっとキメ細やかで深い、何というか「その場での在り方」の圧倒的なやわらかさとオープンさだったのです。
ジャカルタをフィールドワークしながら、街で出会う様々なことに面白がる比嘉さん、その比嘉さんを我々が面白がる入れ子構造。その日の夕方にしたワークショップだけで本が一冊書けそうなほどの相手と自己への気づきがあり。
その日の様子は大石のDiary(2月24日) をご覧いただくとして、ここではある1つのシーンだけにフォーカスしたいと思います。
ジャカルタ2日目、比嘉さんリードのフィールドワーク。地元の小さな通りを歩きながらパサール(市場)に向かう道すがら、角にあるとある飲食店の前で比嘉さんの足が止まる。中に見えるキッチンには、調理の下ごしらえ(?)でひたすら大量のニンニクをむいている女性たち。足を止めた比嘉さんは裏戸から中の様子を少し離れて見ている。そのままポーズして数秒。次に、比嘉さんに気づいた店員と目を合わせつつ様子を見ながら裏戸のヘリ辺りまですーっと移動。最終的には少し中に入りつつ、ちょっとした会話のやり取りをして(現地語はできないはずだけど・・・)満足した様子の比嘉さん、またパサールへ歩き始める。
「Hello!」とか「Hi!」とは入っていきません
このシーン、何が印象的だったかというと比嘉さんの近づき方です。比嘉さんはもちろんにこやかではあったと思うのですが(私は後ろで見ていたので)、決して馴れ馴れしく強引に入っていったりはしません。そして「待つ」のです。目が合って、即こちらが知りたいことを聴くのではなく、自分をひらいたままちょっとのあいだ「待つ」。そして相手の反応に委ねる。これってすごいことだと思いませんか?リサーチャーの皆さん。
何がすごいかというと、相手の反応に委ねるということは自分が聴きたいこととは全く違う展開になる可能性があるということなんです。インタビュー調査では、被験者との限られた時間の中で答えに最短距離で近づきたい。さすがにクローズエンドな質問(Yes/No)にはしないけれど、やはりこちらが会話のリードを取ろうとしがちです。
知るということは、自分の質問の解答欄を埋めていく行為ではない
後で比嘉さんに「待つ」理由を聴いたところ、いわく「話のターン(始まり)を委ねることで、その人の話したいことが分かり、そのことについて聴ける」つまり、自分が知りたいことよりも相手が話したいことを優先させる。この人が「何を伝えたいか」「比嘉さん(という外国人)が何を知りたいと解釈したのか」自体にも有益な情報が含まれているということなんです。むしろ、いろいろな展開が起きうる可能性が開かれているほうが収穫は大きい・・・かもしれない。
お店でニンニクをむいている人は事前に“手配”した被験者ではありません。他にもお店はあるし、ここで自分の興味を全部ぶつけて解消する必要はないんです。どうせ、こちらの問いもまだそれほどシャープなものではないんですから。ちなみにこの時に立ち止まった理由は、「(まだ見れていなかった)調理している現場が見つかったから」だそうです。

効率よりもフラットに出会いたい
このシーンでは、比嘉さんの「たたずまい」も印象的です。いわゆる暑苦しかったり距離が近すぎたりしない。
インタビューやワークショップでは、リラックスして本音を出してもらおうと、まず形や雰囲気からつくりがちです。インタビュアーが「“あたかも”昔からの知り合いのように」、ファシリテーターが「“あたかも”元の性格がフレンドリーでハイテンションであるように」。でもこれって本当は順序が逆ですよね。「それを言っちゃぁ、お終いよぉ」とも言われそうだけど。
ここでもまた、比嘉さんは関係性の起こり方を相手に少し委ねていて、どちらにも行けるように佇んでいます。 そうやって始まるコミュニケーションは短時間で得られる情報量は少なくなるかもしれないけれど、息の長い関係性になる可能性が高い。もちろん、そうならないことのほうが圧倒的に多いから、そういう人に出会うために、買い物をしたりして会話が発生する「母数」を増やす
人類学者って異国に入って生活するんだから、さぞかしラポール(気持ちの架け橋)を誰とでも瞬間的に築ける特殊能力を持っているんだろうと思ったりしますが、実はそうではない。質の高い(という表現が適切かはともかく)コミュニケーションの回路がひらかれるということは、ハリボテではない自然な関係性ができる ということで、そのプロセスはショートカットできない。上手くなることはできるかもしれないけれど。
この後、まだまだ疑問が膨らむ想定なので・・・。
そもそも人類学で行うフィールドワークなら、数ヶ月の滞在や数年の研究になるわけで、誰かと長期的な関係性を築くことが結果として合理的です。また、「今この会話」で疑問が全て解消される必要もありません。それは「別の機会」「家族など他の人」「会話以外(行為などの観察)」でいずれ解決されるかもしれない。ここに、そもそものマーケティングリサーチ(MR)との違いがあることは確かです。MRでは、最初に知りたいことと聴きたい人(のプロフィール)の前提があって、限られた資源の中で最大限確からしい問いの答えを得ようとする。そういう 制約条件の中で洗練されていった「会話風の質疑応答」の技法 ともいえるわけです。その距離感は、むしろ臨床心理学のカウンセリングに近いともいえるでしょう。
方法論とそれが生まれたフィロソフィーは本来切り離せない
しかし、ここで私が共有しておきたいのは、いかに自分たちが 「日本で行うMRのメソドロジー(方法)の常識」に無意識にとらわれているか という気づきです。
・被験者のリクルーティング条件で「アタリ」の確率を高めようとする とか、
・その人には一度きりしか聴けないという前提 とか、
・フィールドワークといいつつ、結局は今ある疑問点を埋める為のインタビュー中心の調査設計 とか、
・家庭訪問調査で初対面の他人にプライベートは見せたがらないから家の中を見せてもらうのはスクリプト(質問の進行表)の最後に回すというコツ とか。
これらは全て、マーケティングリサーチの規範や日本社会で教育を受けて育った人たちが対象という状況に限定されるカッコつきの「常識」で絶対的な真理ではないのです。
また一方で、比嘉さんの視点や方法論はトンガでのフィールドワークにおいて「アンケートやインタビューというやりとりのパターン(相互行為の型)が共有されていない」なかで何とか知りたいことを分かるために編み出されていった方法論であって、人類学者なら誰でも共有している万能の方法ではないということにも注意が必要です。だから私たちが、たとえ人類学の「方法論だけ」を取り出して完コピしても、同じ気づきを得られるわけではない。その 根底にあるフィロソフィーのようなものから体得していく必要があるのです。
人類学の研究のために行う調査とビジネスにおいて特定の目的のために行う調査では前提が違うことも確かです。しかし、この違いを相対主義的にとらえてそのまま置いておくか、その違いがもたらす自身への揺さぶりを、さてどう扱ったものかと「モヤモヤ」「ニヤニヤ」する のとでは後々に大きな違いが生じると思うのです。
※お断わり
言うまでもないことですが、このレポートは比嘉夏子さんのフィールドワークの始まり方を私たちUCI Lab.が参与観察して得られた局所的な気づきであって、一般の人類学全体と一般のデザイン思考(そんなものがあるのは別として)の比較論ではありません。あしからず。